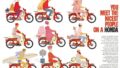特集:Yamaha 2ストローク黄金期(1970–1985)――RDからRZへ、スピードの系譜
1970年代、ヤマハは小排気量で“大排気量を喰う”という価値観を世界に浸透させた。
起点はピストンポート最終期のDS7(1971)、そこからRDシリーズ(1973)でリードバルブ(トルク・インダクション)を導入し、公道での扱いやすさと高回転の伸びを両立。
そして1980年、RZ250が水冷化・モノクロスサスで次世代の車体バランスを提示し、2ストスポーツは“最終進化形”へ到達する。
本コラムでは、技術・市場・文化の3視点で“ヤマハ2スト黄金期”を俯瞰する。
1. 技術の進化 ― 「吸気」
ヤマハ2ストの進化は、まず吸気方式に表れる。
YDS-3(1964)は分離潤滑オートルーブで実用性を確立、DS7(1971)はピストンポート最終進化でシャープな吹けを実現。
転換点はRD250/RD350(1973)のリードバルブ採用。低速トルクが増し、街中でも使えるトルクカーブへ。
1980年代の入口でRZ250(1980)は水冷化と軽量モノクロスで熱・剛性の課題を解決し、総合性能が飛躍した。
2. 市場での評価 ― “Giant Killer”の誕生
2ストは小排気量でも重量・回転レスポンスで優位に立てる。RDは前ディスク・6速を備え、同時期の4ストに対し加速・コスパ・扱いやすさでアドバンテージを築いた。
RZは水冷ツイン+軽量車体で“ナナハンキラー”の異名を獲得。免許制度・若者文化・サーキットトレンドが相乗し、2ストは青春の速度そのものとなった。
3. 文化とデザイン ― “人機一体”の体験価値
ヤマハの2ストは数値だけでなく体感の美学を磨いてきた。
高回転での“カミソリのような”レスポンス、軽い操舵、ブレーキとシャシーのバランス。
人機一体のフィロソフィは、レーサーレプリカ前夜の市販スポーツに凝縮され、RD→RZ→TZRへ受け継がれていく。
4. タイムラインで辿る主要モデル
- 1959:YDS-1 ― 2ストスポーツの原点
- 1964:YDS-3 ― オートルーブで実用性を確立
- 1967:YR-1 ― 350ツインの夜明け
- 1971:DS7 ― ピストンポート最終進化
- 1973:RD250/RD350 ― リードバルブで公道最強へ
- 1980:RZ250 ― 水冷化+モノクロスの新基準
関連記事